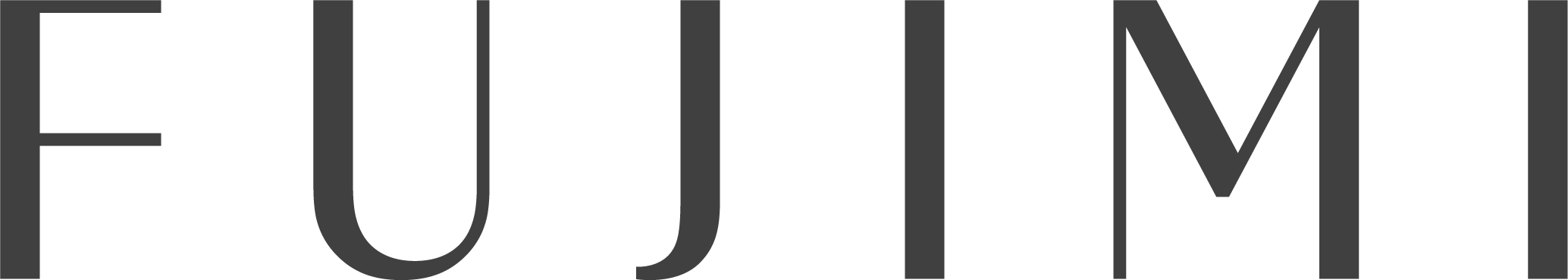カルシウムは骨や歯のもとになると聞いたことがある方は多いでしょう。カルシウムはカラダには欠かせない栄養素で、乳製品や小魚・海藻類に多く含まれています。また、性別や年齢によって摂取する目安量も異なります。
本記事ではカルシウムを多く含む食材や適切な摂取量、カルシウムの過剰摂取による影響、おすすめの献立を紹介しています。
カルシウムの効果的な取り入れ方を知りたい方は、参考にして下さい。
カルシウムを多く含む食材
カルシウムは健康な骨や歯のために欠かせない栄養素で、乳製品や野菜類、豆類、海藻類などさまざまな食品に多く含まれています。
しかし、カルシウムだけを摂取するだけでは充分な働きを発揮できず、マグネシウムやビタミンDの摂取、適度な運動も大切です。
健康を維持するには、規則正しい生活やバランスのとれた食生活が前提となります。ここでは不足しがちなカルシウムを日々の食卓にプラスできるよう、カルシウムを多く含む食材を紹介します。ぜひ日々の食事の参考にして下さい。
カルシウムを多く含む食材①:乳製品
カルシウムと聞くと、多くの人が乳製品を思い浮かべるでしょう。
乳製品には多くのカルシウムが含まれており、スーパーやコンビニで手軽に手に入るため、日々の食卓に取り入れやすい食材です。また、調理の必要がなく食べられるものが多いため、ゆっくりと朝食を摂る時間がない方にもおすすめです。
農林水産省が公開するデータによると、主な乳製品のカルシウム含有量は下記のとおりです(※)。
|
食品名 |
摂取量 |
カルシウム含有量 |
|
牛乳 |
コップ1杯(200g) |
220mg |
|
ヨーグルト |
1パック(100g) |
120mg |
|
プロセスチーズ |
1切れ(20g) |
126mg |
(※)農林水産省「成長期にカルシウムをたくさんとって骨の貯金をしよう」
カルシウムを多く含む食材②:野菜類
乳製品だけでなく野菜にも多くのカルシウムが含まれています。
また、野菜はカルシウムのみでなく、ビタミンも含むため、栄養バランスを考慮して野菜からカルシウムを摂取するのも選択肢のひとつです。
農林水産省が公開するデータによると、カルシウムを多く含む野菜の種類と含有量は下記のとおりです(※)。下記で紹介している野菜は料理にも使いやすいものばかりなので、日々の食事にぜひ取り入れて下さい。
|
食品名 |
摂取量 |
カルシウム含有量 |
|
小松菜 |
1/4束 (70g) |
119mg |
|
菜の花 |
1/4束(50g) |
80mg |
|
水菜 |
1/4束(50g) |
105mg |
|
切り干し大根 |
煮物1食分(15g) |
81mg |
(※)農林水産省「成長期にカルシウムをたくさんとって骨の貯金をしよう」
カルシウムを多く含む食材③:小魚・海藻類
小魚や海藻類にもカルシウムが多く含まれています。小魚は骨ごと食べると、効率よくカルシウムを摂取できるのでおすすめです。
また、一度に大量に食べるのが難しい食材も多いため、ほかの食材と組み合わせて少しずつ食べてみて下さい。
農林水産省が公開するデータによると、カルシウムを多く含む小魚・海藻の種類と含有量は下記のとおりです(※)。
|
食品名 |
摂取量 |
カルシウム含有量 |
|
ひじき |
煮物1食分(10g) |
140mg |
|
さくらえび(素干し) |
大さじ1杯(5g) |
100mg |
|
ししゃも |
3尾(45g) |
149mg |
(※)農林水産省「成長期にカルシウムをたくさんとって骨の貯金をしよう」
カルシウムを多く含む食材④:大豆でできている食材
大豆でできている食品にも、カルシウムが多く含まれています。また、骨の健康に欠かせない大豆イソフラボンも含まれています。大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きもするため、女性は意識して摂りたい食材のひとつです。
農林水産省が公開するデータによると、カルシウムを多く含む大豆製品の種類と含有量は下記のとおりです(※)。
|
食品名 |
摂取量 |
カルシウム含有量 |
|
木綿豆腐 |
約1/2丁 (150g) |
180mg |
|
納豆 |
1パック(50g) |
45mg |
|
厚揚げ |
1/2枚(100g) |
240mg |
(※)農林水産省「成長期にカルシウムをたくさんとって骨の貯金をしよう」
カルシウムとは
カルシウムは健康な骨や歯を作るのみでなく、いくつかの役割があり、不足するとさまざまなリスクがあるため意識して摂りたい栄養素のひとつです。
カルシウムの特徴や役割を知り、食生活に活かして下さい。
カルシウムの特徴
カルシウムは必須ミネラルのひとつで、体重の1~2%と体内に一番多く存在するミネラルです。
体内に存在するカルシウムの99%は骨や歯に使われ、残りの1%は血液や筋肉の働きに関わっています。
しかし、カルシウムは摂取したすべてが体内で使われるのではなく、体内に吸収されるのは20~30%程度で、残りの70%は体外に排泄されていきますが、食品によって吸収率にばらつきがあります。吸収率は、小魚が33%、野菜が19%であるのに対し、牛乳は40%です。
カルシウムの役割
カルシウムには以下のような働きがあります。
- 健康な骨や歯を作る
- 骨粗しょう症を予防する
- 血液凝固を助ける
- 心臓や筋肉を正常に動かす
カルシウムが不足すると、骨や歯が弱くなり骨折しやすくなる、骨粗しょう症のリスクが上がる、腰痛が起きやすくなるなどの可能性があります。そのため、不足しないよう日々の食事から意識的にカルシウムを取り入れる必要がありますが、摂りすぎもよくありません。
カルシウムの過剰摂取には注意が必要
先述したようにカルシウムは摂取した20~30%が吸収されるのみであり、普段の食事では過剰摂取を心配する必要はほぼありません。
しかし、食事以外のサプリメントや薬からカルシウムを摂取した場合には、過剰摂取にならないよう注意が必要です。腎結石や尿路結石の泌尿器系結石の発症や、ほかの栄養素がうまく吸収されない可能性があるからです。
過剰摂取した場合の影響
カルシウムを過剰摂取すると、便秘になる可能性があります。
また、食事からではなくサプリメントや薬から大量のカルシウムを摂取し続けていると、心血管疾患のリスクが上がる可能性もあるため、注意が必要です。
しかし、カルシウムは吸収率が低い栄養素であり、サプリメントや薬からの大量摂取がなければ、過剰摂取を過度に心配する必要はありません。
過剰摂取を防ぐために気をつけること
過剰摂取を防ぐためには、1日3食のバランスのとれた食事からカルシウムを摂取することが大切です。
もし、食事からのカルシウムが不足していると感じ、サプリメントで補おうとする場合は、1日のカルシウムの必要量を考慮して取り入れましょう。
そして、健康な骨や歯のためにはカルシウムだけでなく、ビタミンやたんぱく質のようなさまざまな栄養素が必要だという点を念頭に置き、バランスのとれた食事を心がけましょう。
カルシウムの適切な摂取量
カルシウムは性別、年齢別で推奨されている摂取量が異なります。また、18歳以降では男女関係なく、耐容上限量は2,500㎎/日とされています。
厚生労働省が2019年12月に作成した報告書では、カルシウムの摂取推奨量を次の表で紹介しているので、献立を立てるうえで参考にして下さい。
(単位:mg/日)
|
男性 |
女性 |
|
|
1~2歳 |
428 |
415 |
|
3~5歳 |
587 |
532 |
|
6~7歳 |
585 |
538 |
|
8~9歳 |
645 |
750 |
|
10~11歳 |
708 |
732 |
|
12~14歳 |
991 |
812 |
|
15~17歳 |
804 |
673 |
|
18~29歳 |
789 |
661 |
|
30~49歳 |
738 |
660 |
|
59~64歳 |
737 |
667 |
|
65~74歳 |
769 |
652 |
|
75歳~ |
720 |
620 |
(※)厚生労働省「「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書」
カルシウムを美味しく取り入れられる料理

カルシウムはひとつの食材ではなく、いくつかの食材を組み合わせると美味しく、飽きずに摂取できます。紹介する献立を参考に、普段の食事にカルシウムを取り入れてみて下さい。
- ひじきと小松菜の白和え
カルシウムを多く含むひじきと小松菜、豆腐が摂取できます。
- ツナチーズのサンドイッチ
カルシウムを多く含むツナとチーズが摂取できます。また、ツナにはカルシウムの吸収を助けるビタミンDも含まれています。
- じゃことわかめのサラダ
サラダにすると、野菜からビタミンも摂取できます。じゃこやわかめは一度に多く摂取しにくいですが、サラダのトッピングにして普段から取り入れる方法がおすすめです。
カルシウムの吸収率を上げる工夫
カルシウムは、先述したようにカルシウムの摂取のみではうまく働かないため、カルシウムの吸収率を上げるビタミンDも一緒に摂取するといいといわれています。また、ビタミンDは日光浴によっても生成されるので、散歩などをするのも良いでしょう。
しかし、ビタミンDはほかの医薬品と飲むと働きを弱める場合もあるため、医薬品を内服している場合は、医師や薬剤師に相談して下さい。
まとめ
カルシウムを多く含む食材やカルシウムの働きを紹介しました。
カルシウムは骨や歯を作るミネラルで、乳製品や小魚・海藻類、野菜、大豆からできた食材に多く含まれており、いくつかの食材も組み合わせて摂取するといいでしょう。
そして、カルシウムは普段の食事から摂取する程度であれば、過剰摂取を心配する必要はありません。
また、ビタミンDとあわせて摂取すると、カルシウムの吸収率が上がります。効率的に摂取するためにも、ぜひ普段の食事でも意識して取り入れてみて下さい。
FUJIMIは、みなさまの美容やライフスタイルに関するご相談をいつでも承っております。美容や健康のプロである専任コンシェルジュがお一人おひとりに寄り添いお答えいたしますので、ぜひお気軽にFUJIMI公式LINEにてお問い合わせください。
【監修者】

北嶋佳奈
大学卒業後、飲食店勤務やフードコーディネーターアシスタントを経験し、独立。
2019年に株式会社Sunny and設立。「こころもからだもよろこぶごはん」をテーマに美容・ダイエット・健康に関する料理本の出版、雑誌でのレシピ開発やコラム執筆、ラジオ・テレビ・イベントへの出演などで活動中。
所有資格:管理栄養士